この記事には広告が含まれます。
【新海誠「君の名は。」_感想】時を越えた入れ替わりのトリック
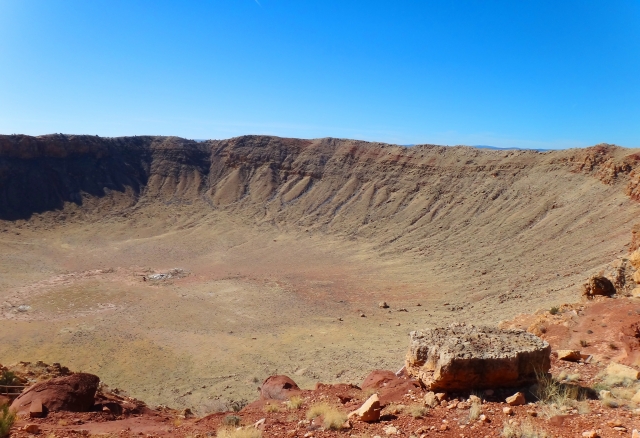
新海誠作「君の名は。」で起こった入れ替わり現象について考察するとともに、前半部の感想を述べていきます。王道のジャンルにも関わらず、映像作品でありながらトリックに気付かせなかった。伏線をはるためにこだわられた背景描写こそ、本作で最もオススメするポイントだと考えています。
目次
瀧と三葉の入れ替わり
以下ネタバレ注意です。
入れ替わりのパラメータ
まずこの入れ替わり現象のパラメータを箇条書きで表します。このとき、他の入れ替わり作品と異なる重要な点を赤字で記しています。
- 当事者:立花瀧(東京で暮らす男子高校生)、宮水三葉(山深い田舎町に暮らす女子高校生)
- 原因:ムスビ(宮水神社に伝わる伝統的な風習)
- 特色:2人の時間軸がずれている
- 精神変化:特になし
- 記憶:引き継がない
- 被害:大きなものはなし。ただし人間関係を悉く変えた。
- 期間:9月5日(予告2より確認できる限り)~10月4日
- 最期:糸守町周辺へティアマト彗星が衝突したこと
ムスビとは
ムスビ、漢字で書くと「産霊」とは土地の氏神に対する古い呼び名であり、何かと何かを繋げる力を持った存在です。第2章にて三葉達が作っていた組紐(糸守の名産品)や、水を飲むような行いも当てはまるそうです。
「よりあつまって形を作り、捻れて絡まって、時には戻って、途切れ、またつながり。それが組紐。それが時間。それが、ムスビ」
透明な水の流れを、俺は考えるともなく想像する。石にぶつかって分かれ、他と混じり、また合流し、全体としてはひとつに繋がったもの。婆ちゃんの言葉の意味はさっぱり解らないけれど、なにかとても大切なことを、俺は知ったような気持ちになる。(pp.88)
第3章半ば、三葉(瀧)達が神体まで行く道中の一幕です。詰みかねない二択を回避するために欠かせないシーンなのですが「他人(三葉)の口噛み酒を捧げる」と書くと複雑な気持ちになります。
瀧と三葉が入れ替わった要因もムスビが繋いだからと考えられます。推測される限り、ティアマト彗星によって糸守が消滅することを事前に防ぐことが理由をでしょうか。
3年間
瀧と三葉は入れ替わっているとき、空間だけでなく時刻も異なる地点に移動しています。その期間が3年間。これを何故予告の時に発覚しなかったのか、について考察していきます。
1つ目の要因が環境の違いです。ど田舎と東京では3年程度の差が存在しなくなるほど、日常環境の違いがありました。見た目が変わる媒体も個体差のあるスマホですし、ニュースでもわざわざ年を記すことはあまりありません。
2つ目の要因としてミスリードがあります。一般的に入れ替わった2人は何処かの場面で遭遇することが大半です。そして予告(上動画の1:05)にて瀧視点で走る三葉が映っていることから、いずれ2人が出会うことを示唆しています。このとき瀧は中学生なのですが、今迄の映像から高校生と錯覚してしまいます。
余談ですが、三葉は入れ替わっているときにカレンダーを見ている筈です。これは予告2でも確認可能であり、9月5日が月曜日と分かります。2016年と合致しており、3年前の9月5日は木曜日でした。
曜日が違うのに、2人が誤差に気付かなかったのかは分かっていません。ただ、カレンダーの描写を意図的に省いていたのは確かです。
入れ替わりの被害
入れ替わり恒例、性格の変化により人間関係を変える被害です。
被害を簡潔に表しているのが、82ページのやり取りです。三葉は瀧に男子の視線やスカートなどの露出への無警戒さやラブレターへの曖昧な返答などを注意しています。一方で瀧は三葉に、ケーキのドカ食いという金の無駄遣いや身勝手な奥寺先輩との交際をしないようにと警告しています。このことは『「君の名は。」予告2』からもはっきりとわかり、痛いレベルの胸の揺れも放映されています。
バスケの授業で活躍した!? 私そういうキャラじゃないんだってば! しかも男子の前で飛んだり跳ねたりしてるですって!? 胸も腹も足もちゃんと隠せってサヤちんに叱られたわよ! 男子の視線、スカート注意、人生の基本でしょう!?
▼
三葉てめえ、ばか高いケーキとかドカ喰いしてんじゃねえよ! 司たちが引いてるだろう、ていうかそれ俺の金だろうが!
▼
(以下、このようなやり取りが4回程続きますが省略)
▼
私は、(俺は、)いないんじゃなくて作らないの!
上記文章が82~84ページに続く2人のやり取りです。日記を通して繋がっているのですが、会ったことがない割に砕けた会話になっています。彼らにとって他人事でない分、真剣に対処しようとしている旨が、感嘆符の多さからうかがえます。
まとめ
今回は「君の名は。」における入れ替わり現象について取り上げました。
予告時点でマイナーな分野ということもあり、予告の出来が素晴らしいことを加味しても興行収入10億くらいの作品と考えていました。まさかあそこまでヒットするとは思っていませんでした。作品の底力以上にメディアの恐ろしさを実感しました。

コメント